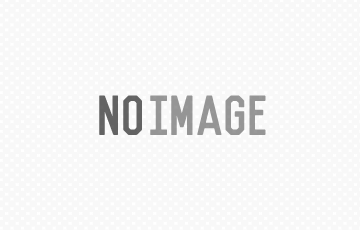ブラックロックとビットコイン:金融構造再設計の物語
はじめに:金融覇者が描く新たな地図
世界最大の資産運用会社ブラックロックとビットコイン。一見交わらなかった両者の関係は、ここ数年で劇的に進化しました。ブラックロックは1988年の創業以来、リスク管理を核に金融界を牽引してきました。一方、ビットコインは2009年に生まれた分散型デジタル通貨で、中央管理者不在の新しい金融の形を提示しています。伝統金融の巨人と革新的な暗号資産、対照的な存在が出会った先に、私たちの金融構造は今まさに再設計されようとしています。
本記事では、ブラックロックCEOであるラリー・フィンク氏のビットコインに対する姿勢の変化から始め、ブラックロックのリスク管理システムAladdin(アラジン)の成り立ちと暗号資産への波及効果を探ります。そして2024年に誕生したブラックロックのビットコイン上場信託IBIT(iShares Bitcoin Trust)の構造と成功要因を分析し、そこから生じた金融構造の3つの変化(価格・流動性・保有者構成)について考察します。さらに、2024年にローンチされたBUIDLファンド(ブラックロックUSDインスティテューショナル・デジタル・リクイディティ・ファンド)の設計思想と意義を解説し、DeFi(分散型金融)との接続が意味する「革命ではなく合併」という視点を提示します。ブラックロックが掲げる三本柱(IBIT・BUIDL・Aladdin)を整理し、ビットコインが「金融構造の試験体」として果たす役割に迫ります。
最後に、ブラックロックの動きから読み解く金融構造再設計の意図と、「中央集権的支配 vs. 共有設計(分散型モデル)」という論点を考察します。その上で、これから世界の金融構造はどう変わるのか、ビットコイン保有はどんな価値を持つのか、そして個人が豊かな未来を送るためにはどの程度のBTC保有が理想なのか—数値的な視点も交えて展望します。記事の結びでは、読者が取るべきアクションの提案(例えば初めてのBTC購入の踏み出し方)も示します。
それでは、物語と分析を交えながら、ブラックロックとビットコインが描く未来図を読み解いていきましょう。
ラリー・フィンクCEOの劇的な変節
ブラックロックのCEO、ラリー・フィンク氏はかつてビットコインに懐疑的な立場で知られていました。2017年、彼はビットコインを「マネーロンダリングの指数」とまで呼び、暗にビットコインは世界中でどれだけ不正資金が動いているかを示しているだけだと酷評していたのです。当時のビットコインは投機的な資産と見なされ、伝統的な金融人にとって受け入れ難いものでした。しかし、そのラリー・フィンク氏がここ数年で大きく舵を切ったのです。
転機は2023年。フィンク氏はFoxビジネスのインタビューで一転してビットコインを称賛し始めました。「ビットコインはどの国にも属さない国際的な資産であり、インフレヘッジや地政学的リスクヘッジとして、金に代わる選択肢となり得る」と述べたのです。これは「デジタルゴールド」という長年ビットコイン支持者が唱えてきた主張を、世界最大の資産運用会社の長が認めた瞬間でした。
そして2024年7月、フィンク氏はついに「自分はビットコインについて間違っていた」と公言しました。CNBCの番組で彼は、「ビットコインは正当な金融資産であり、分散投資にも有用だ。特に世界各国が通貨を濫発し自国通貨の価値を毀損していると感じる時にこそ、ビットコインは一つの投資手段となり得る」と述べ、ビットコインを“デジタルゴールド”になぞらえました。フィンク氏はかつての自らを「誇り高き懐疑論者だった」と振り返りつつ、ビットコインを勉強した結果考えを改めたと語っています。
この劇的な変節の背景には何があったのでしょうか。大きな要因の一つはクライアント(投資家)からの需要です。ブラックロックの顧客には年金基金や保険会社、超富裕層など、世界経済に敏感なお金のプロたちがいます。近年のインフレ率上昇、急激な利上げ、そして2023年前後には米銀の相次ぐ破綻など金融不安もあり、彼ら顧客は資産防衛策としてこれまで以上に真剣にゴールドやビットコインに目を向け始めました。実際、「インフレが手に負えない状況で、通貨価値が下がるリスクに備えるには、供給量が勝手に増やせないビットコインのような資産が有効ではないか」という声が増えていたのです。フィンク氏自身、「各国が通貨を劣化させていると感じるなら、ビットコインは魅力的だ」という趣旨の発言をしています。顧客のニーズに応えることはブラックロックの使命です。「顧客は常に正しい」——10兆ドル超の資産を預かるブラックロックがここまで巨大になれたのも、顧客の声を無視しなかったからこそ。つまり、顧客たちがビットコインを求め始めたので、フィンク氏も自らの見解を改めざるを得なくなったとも言えるでしょう。
こうしたフィンク氏の心変わりは、単なる個人の意見転換に留まりません。世界の金融界に強い影響力を持つ人物がビットコインを認めたことで、暗号資産に対する見方が大きく変わりました。ビットコインは「無視できない資産クラス」として市民権を得たと言えます。実際、2024年にはブラックロックがついにビットコイン関連の金融商品を本格的に投入し、市場参入していきます。それが次章で述べるIBIT(アイビット)と呼ばれるビットコイン信託です。その前に、ブラックロックが培ってきたリスク管理の伝統と、その集大成であるシステムAladdinの話から紐解いていきましょう。
リスク管理思想とAladdin誕生の物語
ブラックロックの物語は、リスク管理の物語でもあります。同社が生まれた1988年、創業メンバーにはラリー・フィンク氏がいました。当時フィンク氏は投資銀行ファースト・ボストンで債券トレーダーを務めていましたが、約1億ドルもの損失を出してしまった過去があります。原因は彼自身ではなくバックオフィスのミスで、ヘッジの計算違いによるものでした。しかしこの痛手がフィンク氏に「精緻なリスク管理ツール」の必要性を強く印象付けます。自分でコントロールできないリスクで巨額損失を被った悔しさから、「ポートフォリオのリスクを正確に測り管理できるシステム」を作るという執念が生まれました。
1988年、フィンク氏は仲間と共にブラックロックを創業します。最初の社員チャールズ・ホラック氏に託された使命が、まさにフィンク氏のリスク管理ビジョンの具現化でした。こうして開発が始まったシステムがAladdin(アラジン)です。Aladdinとは「Asset, Liability, Debt, and Derivative Investment Network」の略称で、資産・負債・債務・デリバティブ投資ネットワークという意味の名が示す通り、あらゆる資産とリスクを一元管理するための社内テクノロジーとして設計されました。
ブラックロックは創業当初からこのAladdinの開発に注力し、全ての投資ポートフォリオの隅々までリスクを把握する文化を築きました。「ブラックロックを本当に理解するには、Aladdinを理解する必要がある」と同社COOのロブ・ゴールドスタイン氏が語るほどに、ブラックロックの中核にはAladdinが据えられてきたのです。1990年代、米国では金利急騰による債券市場崩壊(1994年の債券大虐殺)や、1995年のメキシコ通貨危機など動乱が続きましたが、ブラックロックのファンドはAladdinの助けで最小限の損失に留めました。これにより「自社のポートフォリオを診断してほしい」と他社から依頼が来るようになり、ブラックロックは自社ツールだったAladdinを外部にも提供し始めます。こうしてAladdinは単なる社内システムに留まらず、世界中の金融機関が利用するグローバルなリスク管理プラットフォームへと成長しました。
現在ではAladdinはブラックロック自身の運用資産のみならず、他の資産運用会社や年金基金など240社以上の機関にも提供されており、そのプラットフォーム上で管理される資産規模は21兆ドル以上とも推計されています。まさに「世界金融の隠れたOS」と呼べる存在です。このAladdinの強みは、マーケットのあらゆる商品(株、債券、コモディティ、デリバティブ等)のポジションやリスクを統合的に把握し、シナリオ分析やストレステストを行えることにあります。
Aladdinと暗号資産の出会い
そんなAladdinは近年、暗号資産の世界にもその触手を伸ばしています。ブラックロックは2022年8月、米国最大手の暗号資産取引所コインベースとのパートナーシップを発表しました。この提携により、Aladdinの顧客(機関投資家)はコインベースの機関投資家向けサービス「Coinbase Prime」を通じて、ビットコインなど暗号資産の売買・カストディ(保管)を直接行えるようになったのです。ブラックロックのジョセフ・チャローム氏(戦略エコシステム・パートナーシップ責任者)は声明で「当社の機関投資家クライアントはデジタル資産市場へのエクスポージャー獲得にますます関心を持っており、そうした資産のライフサイクル全般を効率的に管理する方法に焦点を当てている」と述べています。まさに顧客の需要に応じて、Aladdinに暗号資産という新しい資産クラスを組み込んだわけです。
この動きは、伝統的な金融機関が暗号資産に本格参入する重要なシグナルとなりました。コインベースとの提携発表で同社株価が急騰したことからも、市場は「ブラックロックの参入=暗号資産市場の legitimization(正統化)」と受け止めたと言えます。実際、Aladdinに暗号資産が組み込まれたことで、数多くの機関投資家が既存の馴染みあるプラットフォーム上でビットコイン投資を検討・実行できる環境が整いました。言い換えれば、ブラックロックは暗号資産市場への入り口を大きく広げ、橋を架けたのです。
Aladdinが管理する莫大な資産(数十兆ドル規模)の一部が今後暗号資産に振り向けられる可能性を考えると、そのインパクトは計り知れません。さらにAladdin上で暗号資産を扱うことで、リスク管理の観点からもビットコインなどのボラティリティや相関性が従来の資産と比較・分析され、伝統金融のリスクモデルにビットコインが統合されていくことになります。それは暗号資産が金融の本流に組み込まれていくプロセスそのものです。
こうしたAladdinと暗号資産の融合は、ブラックロックが目指す「金融構造の再設計」の第一歩とも言えるでしょう。次に、ブラックロックが2024年に打ち出したビットコイン戦略の核心であるIBIT(アイビット)について詳しく見ていきます。これはビットコインを伝統金融商品として組み込む試みであり、市場に大きな変化をもたらしました。
IBIT誕生:ビットコインETFへの道とその設計
IBIT (iShares Bitcoin Trust) は、ブラックロックが2024年1月にローンチしたビットコインの現物(スポット)連動型上場信託です。いわゆるビットコインETF(上場投資信託)に相当する商品で、ビットコインそのものを保有し、その価値に連動したシェア(株式のようなもの)をNASDAQ証券取引所で売買できるようにしたものです。このIBITの誕生は、ビットコインが伝統的な金融商品として正式に認められた歴史的瞬間でした。
ブラックロックは2023年6月にIBITのSEC(米証券取引委員会)への申請を行いました。当初から市場関係者の期待は高く、「ブラックロックが本気で申請するなら承認の可能性は極めて高い」と噂されていました。その理由の一つは、ブラックロックのETF申請における驚異的な実績です。SECに提出したETF申請576件中575件を承認させてきた(失敗は1件のみ)という記録があり、「ブラックロックが動くときは勝算がある時だけ」という信頼があったからです。実際、業界では「ブラックロックはSECと太いパイプがあるため、彼らが申請するということは水面下でゴーサインを得ているのではないか」とも囁かれていました。
とはいえ、SECは長年にわたりビットコイン現物ETFの承認を拒み続けてきました。理由は市場操作や不正行為への懸念でした。しかし2023年8月、米控訴裁判所(DCサーキット)は「SECがグレースケール社のビットコイン現物ETF転換申請を却下したのは恣意的で矛盾している」と判断し、SECに再考を命じる判決を下しました。この裁定により、SECの態度も軟化します。2024年1月10日、ついにSECはブラックロックのIBITを含む計11本の現物ビットコインETFの一斉承認に踏み切りました。ゲンスラーSEC委員長も判決を踏まえ「現状を踏まえれば承認が最も持続可能な道だ」とコメントしています。かくして、ビットコインETF(信託)は日の目を見ることになったのです。
IBITの構造設計:受け入れられた理由
IBITが当局に受け入れられた背景には、その巧みな構造設計があります。IBITはグレースケール社のビットコイン投資信託(GBTC)の問題点を解決するよう設計されました。グレースケールのGBTCは従来からビットコイン投資手段として存在しましたが、「保有ビットコインを投資家が直接引き出せない(現物交換できない)」という欠点があり、市場価格が基準価値から大きく乖離する問題がありました。IBITではこれを避けるため、Authorized Participant(AP:指定参加者)と呼ばれる証券会社がビットコイン現物との交換(インカインド・レデンプション)を行える仕組みにしています。具体的には、APはIBITのシェアと引き換えにビットコイン現物を信託とやり取りでき、その裁定取引によってIBITの市場価格が常にビットコイン実勢価格(NAV)にほぼ一致するよう調整されます。このインカインド赎還の仕組みはETFでは一般的ですが、GBTCには無かったものです。IBITはそれを導入することで投資家にとってフェアな価格形成を実現しました。
また、IBITは税制面でも有利なグラントール・トラスト(grantor trust)という形態を採用しました。これにより投資家はIBITシェアを通じてビットコインを間接保有していても、税法上はビットコイン現物を保有しているのと同じ扱いを受けます。例えばビットコインを長期保有した場合の低いキャピタルゲイン税率の適用など、直接保有に近いメリットが得られるのです。グレースケールのGBTCでは売却時に常に課税される不利がありましたが、IBITはそれを解消しました。
さらに、SECが懸念していた市場操作対策にもIBITは万全を期しました。ナスダック取引所と主要な現物ビットコイン取引所(具体的にはコインベースと推測されます)が監視共有協定(Surveillance-Sharing Agreement, SSA)を結ぶことを提案に盛り込み、市場データや不正の情報をリアルタイムで共有して操作を検知・抑止する体制を整えたのです。このSSAによって不透明な海外取引所での価格操作があっても検出しやすくなり、SECも一定の安心感を得られました。
IBITの保管カストディにはコインベースなど信頼性の高いカストディアンを起用し、価格参照には複数の主要取引所からなる指数を用いることで、価格の信頼性と透明性も確保しています。こうした総合的な設計により、IBITの提案は「過去の申請と比べ格段に筋が良い」と評価されました。上述の法的状況の変化(裁判所の判断)も追い風となり、IBITは承認に至ったのです。
では、このIBITが市場にもたらしたインパクトとは何だったのでしょうか?次に、IBIT誕生後に起きた価格・流動性・保有者構造の3つの変化について見ていきます。
IBIT成功のインパクト:価格・流動性・所有者の3つの変化
1. 価格:ビットコイン市場に史上最高値と安定をもたらす
IBITのローンチはビットコイン価格に大きな影響を与えました。2024年はビットコインにとって飛躍の年となり、価格は上昇トレンドを強めました。そして2025年初頭、ビットコインはついに過去最高値を更新し9万3千ドルに達しました。ブラックロックのIBITをはじめとする現物ETFへの巨額資金流入が、その原動力の一つとされています。IBIT自体の保有ビットコイン量が膨張したことにより、市場の需要が大きく押し上げられたのです。また、価格の上昇とともにビットコインの資産クラスとしての地位も向上しました。2025年時点でビットコインの時価総額は一時1.7兆ドルを超え、世界資産ランキングで銀(シルバー)を追い抜き世界第7位の資産に躍り出たとの報告もあります。
興味深いのは、価格上昇と同時に市場の安定性も増したと指摘される点です。現物ETFはビットコイン価格に連動して即座に現物の売買を伴うため、現物市場に常に買い需要と売り需要のクッションが存在する形になります。例えばIBITのシェアが大量に買われれば、APがビットコイン現物を市場で買い付けて信託に納めるので価格が上がりますが、逆にIBITが売られればAPが現物を売却します。こうした裁定メカニズムが働くことで、価格が急騰急落する際にもある程度のバッファーができ、市場変動が緩和される効果があると考えられます。実際、IBIT開始後は週末(従来は取引参加者が少なく乱高下しやすい)におけるビットコインの出来高・ボラティリティが低下したとの分析もありますETFという伝統市場の規律がビットコイン市場にもたらされたとも言えるでしょう。
2. 流動性:かつてない資金流入と市場の厚み
IBITはビットコイン市場に大量の資金流入を呼び込み、流動性を飛躍的に高めました。ローンチ初日、米国で立ち上がった複数のビットコインETF合計で22億ドル超の売買高を記録し、うちブラックロックのIBITだけで約10億ドルを占めたというデータがあります。この数字はETF業界の新記録であり、市場の関心の高さを物語っています。IBITはローンチ直後から連日資金流入が続き、初の営業四半期(2024年Q1)だけでブラックロック全ETFへの資金流入の21%がIBIT一つに集中するほどの人気となりました。2024年末までに、IBIT単体で約372億ドルもの純流入を記録し、年間資金流入額で全ETF中トップ3に入ったとの報告もあります。IBITの運用資産残高(AUM)は2024年末までに約332億ドルに達し、ブラックロックが長年運用してきた金ETF(iShares Gold Trust, 現在約320億ドル)をも上回りました。
市場全体で見ると、米国における複数のビットコイン現物ETFを合わせた運用資産は約1,200億ドルに達し、伝統的な金ETFの残高(約1,250億ドル)に匹敵する水準となりました。これはビットコイン市場にそれだけの資金が新たにロックインされたことを意味します。参加プレイヤーも広がり、ETFを通じて今まで直接ビットコインを扱えなかった機関や投資家層が市場に参加可能となりました。結果として板(オーダーブック)の厚みが増し、大口の売買にも耐えられる市場流動性が確保されつつあります。「現物ETFの登場でビットコイン市場の流動性は飛躍的に向上した」とする専門家の声もあります。
もっとも、ETFの仕組み上、IBIT自体の取引は株式市場の取引時間内(平日昼間)に限定されます。しかしビットコイン現物は24時間365日取引されています。このギャップは残りますが、大口投資家にとっては時間外でも先物など他の手段でヘッジが可能ですし、何より平日昼間の出来高が増えたこと自体が市場全体の安定に寄与しています。加えて、他国(例えば欧州やカナダ)の現物ETFとも相まって、世界中でビットコインへの資金流動性が高まったことは確かです。
3. 所有者:ビットコインホルダー構造の変化
IBITの登場はビットコインの保有者層にも変化をもたらしました。かつてビットコインの供給の多くは個人投資家や初期からの暗号資産マニアが握っていましたが、今や相当量がETFという形で機関投資家に代替保有されるようになっています。2025年4月時点で、米国のビットコインETF全体が保有するビットコインの推定残高は、創始者サトシ・ナカモトの保有量(約110万BTCと言われる)に迫る勢いだと報じられました。つまり、全ビットコインの数%以上がETF経由で間接保有されている計算になります。この割合は今後さらに上昇する可能性があります。
ブラックロックのIBIT一つを取っても、2025年1月時点で運用資産残高が約600億ドルを超え、世界の全ETF中31位、ブラックロックのETFとしては400本以上の中で11位の規模に成長しました。これはIBITが約60,000BTC以上(価格によりますが)の現物を保有していることを意味し、単一のファンドとしてビットコイン最大の保有主体となったことを示唆します。実際、2024年5月にはIBITがそれまで世界最大だったグレースケール社のGBTCを抜いて「世界最大のビットコインファンド」となったと報じられました。
このように保有構造が変化したことには賛否あります。一方で「ビットコインが広く分散して保有されるようになった」と肯定的に捉える向きもあります。ETFを通じて一般の投資信託や年金基金にもビットコインのエクスポージャーが組み込まれ始め、事実上ビットコインがマス層の資産形成に組み入れられたとも言えるからです。例えばブラックロックは自社の債券ファンド(退職者向けの安定運用ファンド)にIBITのシェアを組み入れるリバランスを行い、収益源としてビットコインを一部活用し始めました。これは「退職者が間接的にビットコインを持つ」ことを意味します。ビットコインが専門家だけでなく老後資産の一部になり得る時代が来たとも言えるでしょう。
他方で懸念もあります。それはビットコインの中央集中的な保有が進むリスクです。ETFや信託を介すると、実際のビットコインの保管・管理はブラックロックのような一部企業に集中します。ビットコインの理念である「管理者なき分散」が損なわれ、カストディアンが巨大権力を持つ可能性があります。また、IBITの仕組み上、一般のIBIT投資家はビットコイン現物を引き出せません。引き出し(交換)できるのはAPという一部の金融機関に限られ、個人はIBITシェアを売却して現金化するしかありません。極端な場合、伝統金融の論理でビットコインが運用され、貸株(貸コイン)のようなレバレッジ供給(再担保)も行われ得ます。そうなると、ビットコインの発行量上限(2100万枚)以上に「疑似的な売り物」が作られ、価格抑制要因になる恐れもあります。こうした点については後ほど「中央集権vs共有設計」の節で触れますが、IBIT成功の裏側でビットコイン保有構造に新たな課題も生まれているのです。
総じて、IBITの成功はビットコイン市場にもたらした良い変化(価格の上昇と安定化、流動性の向上、投資家層の拡大)と、新たな論点(中央集中的な保有リスク)を浮き彫りにしました。次に、ブラックロックが同時期に進めるもう一つの金融革新、BUIDLファンドについて見ていきましょう。こちらは「トークン化されたドル建て資産運用」の先駆けであり、DeFiとの融合という観点で非常に興味深い動きです。
BUIDLファンドの設計と意義:伝統資産のトークン化
2024年3月、ブラックロックは社史上初となるトークン化ファンドを立ち上げました。その名もBUIDL(ビルド)ファンド、正式名称は「BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund」です。BUIDLはブラックロックの最初のトークン化マネーマーケットファンドであり、伝統的な金融商品をブロックチェーン上で取引可能な暗号トークンとして提供する試みです。
マネー・マーケット・ファンド(MMF)とは、短期国債やコマーシャルペーパーなど信用度が高く流動性の高い短期債券に投資し、元本の安定と僅かな利回りを提供する金融商品です。銀行預金より少し利回りが良い「一時的な資金置き場」として世界中で広く使われています。BUIDLは、この伝統的なMMFをブロックチェーン上でトークン化したものです。具体的には、投資家は1ドルをBUIDLトークン1枚として購入でき、その資金はファンドを通じて米国短期国債や短期貸出(レポ取引)など安全資産に運用されます。ファンドから生じる利息は日々計算され、毎月末に新たなBUIDLトークンが投資家のウォレットに配布される形で還元されます。BUIDLトークンの価値は常に1ドルにペッグ(連動)されるよう設計されており、いわばブロックチェーン版のドル建てMMFです。
このBUIDLの何が画期的かと言えば、大手資産運用会社が公募ファンドをブロックチェーン上で発行した点です。ブラックロックはSecuritize社(セキュリタイズ、証券トークン発行プラットフォーム)と組み、イーサリアムやソラナなど複数のパブリックブロックチェーン上でBUIDLトークンを発行・運用しています。2025年3月末時点で、BUIDLはイーサリアム、ソラナ、アプトス、アルビトラム、アバランチ、オプティミズム、ポリゴンの7つのブロックチェーン上で稼働しており、3週間で運用資産額が6億6700万ドルから18億ドルへと急拡大する爆発的成長を遂げました。ローンチから1年で時価総額が10億ドルを超え、トークン化国債市場全体(約50億ドル)のかなりのシェアを占める存在に成長しています。この成功は、市場に眠っていた需要を掘り起こした証と言えるでしょう。
BUIDLのメリットは、投資家が従来のMMFの安全性と利便性を享受しつつ、ブロックチェーンの持つ24時間取引と即時決済の恩恵を受けられる点にあります。通常、伝統的なMMFの買戻し(換金)は営業日の限られた時間内でしか行えず、送金や決済にも時間がかかります。しかしBUIDLトークンであれば、土日深夜を問わず世界中で売買可能で、トークン間の取引はブロックチェーン上で即時に記録・完了します。これにより資金繰りの柔軟性(流動性)が飛躍的に向上し、カウンターパーティリスクもスマートコントラクトによって軽減されます。実際「伝統資産にブロックチェーンを組み合わせることで、決済に日数かかっていた従来金融を秒単位に短縮でき、非効率に滞留していた巨額の資金を即座に再投資できるようになる」とフィンク氏自身も強調しています。
BUIDLのようなハイブリッドな試みは、伝統金融(TradFi)と暗号資産(crypto)の間に橋を架けるものです。ブラックロックが巨額の資産運用ノウハウと規制対応力を持ち込み、暗号側の技術(トークンとブロックチェーン)を活用することで、双方の長所を生かした新商品が生まれました。ブラックロックと提携したセキュリタイズ社CEOのカルロス・ドミンゴ氏は「BUIDL開始後、伝統的機関投資家からのRWA(現実世界資産)のトークン化需要が想像以上に高まっている」と述べ、高速・低コストで知られるソラナなど複数チェーンへの拡張は自然な次のステップだったと語っています。
さらに興味深いのは、BUIDLがDeFi(分散型金融)コミュニティからも支持を得ている点です。例えばオンチェーン資産運用を手掛けるOndo Finance(オンド・ファイナンス)というプロジェクトは、独自のトークン化短期国債ファンドから約9500万ドルをBUIDLに乗り換えたとされています。これはブロックチェーンネイティブなプロジェクトが、信用力と実績のあるブラックロックのトークン化ファンドを積極的に利用した例です。MakerDAO(メイカーDAO、分散型ステーブルコイン発行プロトコル)も2024年に約10億ドルの準備金を米国国債など現実資産に振り向ける方針を打ち出し、その一部をブラックロック系ファンドに配分しています。つまり、暗号資産側が伝統金融のプロダクトを取り込み、逆に伝統金融側が暗号技術を活用するという融合現象が起きているのです。
DeFiとの融合:“革命”ではなく“合併”
ビットコインやDeFiが台頭した頃、一部では「伝統的な銀行や金融はやがて不要になり、ブロックチェーン革命がすべてを置き換える」という極論も語られました。しかし現実に起きているのは、革命による一方的な破壊ではなく、巨人(ブラックロック)の側から差し伸べられた手による合併・融合です。
ブラックロックの一連の戦略(IBITでビットコインを取り込み、BUIDLで伝統資産をトークン化し、Aladdinでそれらを管理する)は、従来金融と暗号金融を統合しようという動きに他なりません。これはある意味「DeFiの敗北」ではなく、「DeFiの勝利」とも言えます。なぜなら、ブロックチェーンやトークン技術の有用性をブラックロックのような大手が認め、自ら活用し始めたからです。フィンク氏自身、「全ての株式、債券、ファンド——あらゆる資産をトークン化できる。そうなれば投資の在り方は革命的に変わるだろう」と2025年の書簡で述べています。市場はもはや閉じる必要がなくなり、現在は決済に日数を要する取引も数秒で清算され、清算待ちで遊休化している何千億ドルもの資本が即座に経済に還流できる、と彼は熱く語っています 。
この言葉からわかる通り、ブラックロックはブロックチェーン技術の革命性を認識しています。ただし彼らはそれを「自分たちの手で実現する」道を選びました。ビットコインやDeFiが既存の金融システムを破壊するのを待つのではなく、自らその技術を取り込み融合する道です。それは言わば「合併(merger)」のアプローチです。
もちろん、ブラックロックが主導権を握る融合には注意も必要です。巨大プレイヤーの参入によって市場は安定し信頼性は増す反面、集中とコントロールが進む可能性があります。DeFiは本来、誰でもアクセスでき仲介者無しで金融サービスを利用できることを目指しました。しかし現状、BUIDLなどは規制上適格な投資家のみ利用可能であったり(一般人は直接購入できず、プロ投資家向けの私募ファンド扱い)、結局カストディは中央集権的な機関に依存しています。このため、「表面的にはブロックチェーンを使っていても、結局旧来型金融と変わらないのでは」という批判もあります。
しかし一方で、BUIDLの例で見たように、そのトークンはパブリックチェーン上に発行されるため、DeFiプロトコル上で組み合わせて活用することも可能です。事実、前述のようにDeFi側がBUIDLを利用する動きも出ています。革命ではなく合併——すなわち従来金融と新興の暗号金融が歩み寄り、お互いの強みを融合させる方向性は、対立よりも建設的であるとも言えます。ブラックロックは「自分たちが変化に適応し、業界標準を作ってしまおう」という姿勢を示したわけです。
このような融合が進めば、将来的には「中央集権 vs. 分散」の境界は曖昧になるでしょう。大事なのは技術そのものより、その使い方とガバナンスです。ブラックロックが握るハンドルが公正に回されるのか、それとも都合のいいように使われるのか。次章では、この「中央集権的支配 vs. 共有設計(分散ガバナンス)」の論点について掘り下げます。そしてブラックロックがなぜビットコインを“構造試験体”に選んだのか、その意図も考えてみましょう。
ブラックロックの三本柱:IBIT、BUIDL、そしてAladdin
ここで一度、ブラックロックが進める金融再設計の三本柱を整理しましょう。それはすなわち IBIT、BUIDL、Aladdin の3つです。
-
IBIT(アイビット) – ビットコイン現物ETF(信託)として、世界中の投資家に「デジタルゴールド」ビットコインへのアクセスを提供する柱です。これによりビットコインは伝統ポートフォリオに組み込みやすい資産となり、金と肩を並べる存在感を獲得しました。ブラックロックはIBITを通じて暗号資産そのものを自社の商品ラインナップに加え、市場支配力を発揮しています。
-
BUIDL(ビルド)ファンド – トークン化ドル建てMMFとして、伝統金融商品のブロックチェーン上での運用を切り拓いた柱です。投資家にとっては利便性と安定利回りを24/7で享受できる新しい選択肢となり、暗号資産側にとってはRWA(現実資産)の導入という大きな一歩です。ブラックロックはBUIDLで伝統資産のトークン化を実証し、今後のさらなる資産トークン化(株式や社債、不動産など)の布石を打っています。
-
Aladdin(アラジン) – そして両者を繋ぐテクノロジーとデータの基盤です。Aladdinはリスク管理プラットフォームとして、IBITやBUIDLで扱われる従来とは性質の異なる資産(ビットコインやトークン)も包括的に捉え、ポートフォリオ全体でのリスク・リターンを分析します。さらにコインベース連携によって、Aladdinは暗号資産売買のインフラでもあります。ブラックロックはAladdinによって新旧の金融商品を一元的に管理・提供し、クライアント基盤(Aladdin利用者)に対してシームレスなサービスを実現しています。
この三本柱は互いに補完し合っています。Aladdinがエンジンとなり、IBITで得た暗号資産へのアクセスと、BUIDLで得たトークン化技術による効率性を組み合わせ、ブラックロックは「次世代の金融インフラ」を構築しようとしているのです。それは同社CEOの言葉を借りれば「全ての資産がトークン化され、誰もが常時アクセスできるマーケット」であり、その先駆けとしてビットコインとドル資産で実験をしている段階とも言えます。
では、なぜビットコインがその「実験材料(試験体)」に選ばれたのでしょうか? 次の章で、ビットコインが果たす役割とブラックロックの真の狙いについて考察します。
ビットコインは“構造試験体”:金融リニューアルの実験台
ブラックロックがビットコインに注目する理由の一つに、ビットコインが金融構造改革の「ストレステスト」に最適な対象だという点が挙げられます。ビットコインは非常にボラティリティ(価格変動)が大きく、かつ24時間休みなく取引され、分散的に管理されています。このような資産を取り込むことは、伝統金融の枠組みにとって大きな挑戦です。しかしだからこそ、ビットコインで上手くいけば他のあらゆる資産にも応用できるという「試験体」としての価値があるのです。
例えば、ブラックロックが構想する将来像——「株式や債券をトークン化し、市場を常時開放する」という世界を実現するには、多くの技術的・制度的ハードルがあります。市場のボラティリティ管理、流動性確保、投資家保護、不正防止など、多方面の問題を解決しなければなりません。ビットコインは既にその極端なケースを提示しています。急騰急落への対応や、週末夜間の流動性不足、ハッキングリスクや不正取引など、ビットコイン市場で顕在化する課題は、将来的にあらゆる資産のトークン市場でも起こり得るものです。
ブラックロックはIBITを通じて、ビットコイン市場でこれら課題に対処するノウハウを蓄積していると考えられます。実際、前述したIBITの設計(SSAによる監視強化、インカインド赎還で裁定機能確保、信頼できるカストディ活用など)は、将来他の資産クラスをトークン化する際の教訓となるでしょう。ある意味、ビットコインという「野生の荒馬」を手懐けることで、トークナイズされた金融市場全体を制御する手綱の使い方を習得しているのです。
またビットコインはその希少性と普遍性もあって、テストケースとして適任でした。発行上限2100万BTCという枠があるため、需給バランスがダイレクトに価格に反映されやすく、ETF導入による需給変化を観測しやすかった点があります。そしてビットコインは国境を越えたグローバル資産であり、特定の企業収益や国家経済に依存しないため、純粋に「新しい金融構造」の影響を測ることができます。他の株式や債券だと、トークン化以外の要因(企業業績や政策)が絡んで分析が難しいですが、ビットコインなら比較的シンプルです。
さらに、ビットコインには依然として批判的・懐疑的な声も根強くあります。例えばJPモルガンのジェイミー・ダイモンCEOがビットコインを詐欺呼ばわりしたり、政府当局者がマネロンや犯罪利用を懸念したりという話は今もあります。しかしブラックロックの参入によって、ビットコインの正当性が担保され、議論は「ビットコインは是か非か」という段階から「どう扱うべきか」という具体論に移りました。フィンク氏が「私は間違っていた、ビットコインは合法的な金融商品だ」とまで公言したことの影響は大きく、もはや主流金融のテーブルでビットコインが正式に議題に上るようになったのです。
総合すると、ビットコインはブラックロックにとって「金融構造再設計」に必要な実験材料であり、かつ旗艦製品でもあります。実験材料としては、これまで触れたように新機軸を試す場であり、旗艦製品としては顧客流入を呼び込むキラーコンテンツです。実際、IBITの成功がブラックロックにもたらした手数料収入や資金流入は莫大ですし、同社の2024年通年の新規資金流入記録に大きく貢献したとも言われます。つまり、ビットコインはブラックロックにとって「ビジネスとしておいしい」上に「将来戦略にも資する」一石二鳥の存在なのです。
では、ブラックロックが描く金融構造再設計の最終的な意図とは何でしょうか? それは素直に考えれば、自らが新時代の金融インフラの覇者となることです。株も債券も不動産も通貨も、すべてトークン化されAladdinの上で取引・管理される未来——その中心にブラックロックが君臨する姿を目指しているとも取れます。フィンク氏は「トークン化された世界では、今より取引がずっと効率化され成長が加速する」と述べつつ、「ただ一つ解決すべきはアイデンティティ認証(デジタルID)の問題だ」とも指摘しています。匿名性が高い現行の暗号資産システムではなく、身元確認されたうえで安全に使えるトークン経済を作りたいというのが彼の展望です。その実現には中央集権的な管理もある程度必要という考えでしょう。
これに対し、暗号資産コミュニティには「それでは結局中央集権的な管理社会になるだけではないか」という警戒感もあります。ビットコインが夢見たのは、政府や大企業に依存しない自律分散的な金融の形です。ブラックロックの戦略はそれを取り込みつつも、自らがハブとなる形で再編しようとするものです。この是非については議論が分かれるところでしょう。
次章では、こうした中央集権的支配 vs. 共有設計(分散モデル)の論点を整理しつつ、ここまでの教訓と今後の展望をまとめます。そして個人として私たちがどう備えるべきか、ビットコインをどのようにポートフォリオに位置付ければ豊かな未来を築けるのかを考えてみます。
中央集権的支配 vs. 共有設計:金融構造再設計を巡る論点
ブラックロックが推し進める金融構造の再設計には、中央集権的コントロールと分散型の共有設計という二面性があります。一方では、巨大な金融機関が主導権を握り、ルール作りからインフラ運営までを牛耳る中央集権的な未来。もう一方では、ブロックチェーン技術によって誰もがネットワークを検証・参加できる分散的な未来。現実にはこの二つの要素が混在しつつ進んでいます。
ブラックロックの支配力が強まるリスク
まず中央集権的側面の懸念から。ブラックロックがこれだけ暗号資産市場に入り込み、ETFやトークン化ファンドを通じて大量の資産を管理すると、市場に対する発言力・影響力が極めて大きくなります。例えばビットコインETFの保有比率が高まれば、ブラックロックが何らかの理由で買いを停止したり売却を促したりすれば、市場に与えるインパクトは甚大です。また、IBITのような信託では、最終的なカストディアンや運営者であるブラックロックがネットワーク上の資産を制御できる立場にあります。万が一規制当局からの圧力や地政学的リスクで「特定の住所(ウォレット)のビットコイン送付禁止」等の措置が取られた場合、ブラックロックはそれに従うでしょう。これはビットコイン本来の“誰にも止められないトランザクション”という性質と相反します。
さらに技術的な点では、先述の再担保(レンディング)の問題があります。伝統金融ではETF等が保有資産を貸し出す(レンディング)ことで追加収益を得るのは一般的です。ブラックロックもIBITのビットコインを投機筋に貸し出し、ショート(空売り)の担保などに使わせることが考えられます。そうすると実際より多い売り圧力が市場にかかり、価格形成が歪む恐れがあります。ビットコインの思想は「真に裏付けのある1枚」を大事にすることですが、金融工学が絡むとペーパーBTC(紙のビットコイン)が増殖しうるのです。
加えて、ブラックロックが提唱するトークン化世界では、前提としてデジタルID(個人認証)が不可欠とされています。匿名のウォレットではなく、KYC(本人確認)済みのウォレットだけが参加できるネットワークになる可能性があります。そうなると、参加者全員が監視下に置かれ、取引履歴も追跡可能な社会インフラが構築されます。これは透明性向上というメリットがある反面、プライバシーや自由の観点で危惧する声もあります。「すべての資産がトークン化され、すべての人がIDで紐付けられる」という世界は、究極の中央集権管理社会ともなり得るからです。
分散型モデルとの調和は可能か
しかし、一方でブラックロックの動きが完全に中央集権かと言えば、そうとも限りません。BUIDLの例で見たように、彼らは自社プライベートブロックチェーンを使ったわけではなく、既存のパブリックブロックチェーン(イーサリアム等)に乗っかったのです。つまり、オンチェーン上のトランザクション自体は誰でも検証可能で透明です。Ondo FinanceのようなDeFiプロトコルもBUIDLトークンを組み込むことができました。これはブラックロックが既存コミュニティとの互換性を重視したことを示します。完全に自前の閉じたシステムにしなかった点は評価できるでしょう。
また、IBITにおいてもブラックロックは価格指標に複数の分散型取引所(DEX)のデータを入れることも検討しているとされています(※具体的な導入は未確認ですが、CF Benchmarksなどの指標会社はDEXも考慮)。今後、ETFとスマートコントラクトを連動させ、オンチェーンでETFシェア取引を行う試みも出てくるかもしれません。実際他社では、オンチェーンで取引できる上場投信の発行(例:シンガポールのデジタル取引所による債券ETFのトークン化)などの実験も進んでいます。
理想を言えば、中央集権の強み(安定性・信用・規制遵守)と分散型の強み(オープンアクセス・透明性・イノベーション)を両立させることです。ブラックロックはその両者の折衷点を探っているようにも見えます。例えばデジタルIDに関しても、一企業がデータを独占するのではなく、各国政府や独立機関と協調し標準化する必要があるとフィンク氏は述べています。これは一社独裁にはならない余地を残しています。
また、市場参加者にとって重要なのは選択肢です。ブラックロック経由のビットコイン投資が嫌なら、自分でビットコインを買い自分で保管することも依然可能です。BUIDLが嫌ならUSDCなど他のステーブルなDeFi商品もあります。つまり、ブラックロックの新金融構造が出来上がったとしても、それ以外の自由な経路が完全に閉ざされるわけではありません。むしろブラックロックが動いたことで、政府の規制も含めた全体の環境整備が進み、結果として一般ユーザーがより安心してビットコインやDeFiを利用できる基盤が整う可能性もあります。「公式ルート」と「直接ルート」の両方が存在し競争することが、バランスの取れたエコシステムを生むでしょう。
要は、中央集権と分散のどちらか片方ではなく、ハイブリッドな設計が現実解となりそうです。ブラックロックはその主導権を握りたいわけですが、完全に締め付けると利用者が離れイノベーションも起きないため、適度にオープンにする動機もあります。今後、他の巨大金融機関やテック企業、ひいては各国政府も加わって設計競争が起きるでしょう。どの程度の自由と管理を織り交ぜるか、その社会実験が今始まったと言えます。
最後に、こうした状況下で我々個人はどうすべきかという観点に立ち戻りましょう。ブラックロックの動向を踏まえ、これからの世界の金融構造、ビットコインの価値、そして豊かな未来を築くためのビットコイン保有戦略について、具体的な教訓と展望をまとめます。
教訓と今後の展望:新たな金融構造とビットコインの価値
世界の金融構造はどう変わるのか
ブラックロックが示した方向性は明確です。「あらゆる資産のデジタル化・トークン化」と「市場インフラの効率化・常時化」です。今後5~10年で、株式や債券、不動産、コモディティに至るまで、現実世界の資産がブロックチェーン上にデジタル証券として発行され、24時間取引される世界が到来するかもしれません。それは現在の金融市場を一新する大変革です。証券取引所は今の姿を変え、ブロックチェーン上のスマートコントラクトに役割を譲るかもしれません。銀行の送金網もCBDC(中央銀行デジタル通貨)やステーブルコイン、トークン化銀行預金に置き換わっていくでしょう。
しかし、その過程は革命というより漸進的な統合になると予想されます。つまり、既存の大手金融機関や取引所が自らのシステムをアップデートし、規制当局と連携しながらトークン化を進めていくでしょう。ブラックロックのような資産運用会社だけでなく、NASDAQやNYSEといった取引所もデジタル資産の上場に踏み切る可能性があります。実際、ナスダックは暗号資産カストディ事業への参入準備を進めていました(※2023年に計画中止報道がありましたが、市場次第で再開もあり得ます)。また各国の中央銀行はCBDC実験を重ねています。これらが結びつけば、トークン経済圏と既存金融圏の融合は避けられないでしょう。
一方で、全てがブロックチェーンになるわけではありません。高頻度取引(HFT)や超低遅延が必要な一部取引は従来型システムの方が効率的な場面もあるでしょう。また、すべての資産を常時市場に晒すことが本当に良いのかという議論もあります(人々が四六時中価格を気にしてしまう社会が健全かという問題)。ですので、新金融構造は徐々に調整されつつ広がるはずです。おそらくハイブリッド市場が当面は続き、トークンと従来証券が併存する時期がしばらく続くでしょう。
しかし方向としては、一度技術の優位性を知ってしまった以上、後戻りはしません。インターネットがそうであったように、ブロックチェーンによる金融インフラの刷新は、一時的なドットコムバブル的後退があっても長期的には進むと思われます。世界の金融構造はよりフラットでオープンになり、地理的・時間的な壁が低くなるでしょう。送金に国境はなくなり、個人も小口資産をグローバルに分散投資できる時代が来るかもしれません。ブラックロックはその一翼を担いつつ、ビジネスチャンスも享受する腹づもりでしょう。
ビットコイン保有の価値:デジタルゴールドとしての地位
こうした変化の中で、ビットコインが持つ価値は一層際立つ可能性があります。なぜなら、ビットコインは金融構造再編の「試験体」であると同時に、その新構造下で価値の基軸になる潜在力を備えるからです。
フィンク氏が認めたように、ビットコインはインフレヘッジであり、通貨価値下落への保険です。各国が財政赤字を膨らませ通貨を増発している状況で、発行上限があり希少性が保証されたビットコインはデジタル時代のゴールドとして魅力が増しています。現に2020年代前半のインフレ局面で、ビットコインはゴールドと同様の避難先として機能し、価格を上げました。また、ウクライナ情勢など地政学リスクが高まった際に、自国通貨が信用できない国の国民が資産防衛のためビットコインを利用するケースも増えています。ブラックロックがグローバル展開する中で、各国の不安定さに晒されない中立資産としてビットコインの価値を見出したのも当然でしょう。
さらに、金融がトークン化されデジタル化すると、信用という概念の透明化が進みます。21世紀に入ってからの幾度もの金融危機(リーマンショック、欧州債務危機、コロナショックなど)は、信用創造の過剰やデリバティブの不透明さが要因でした。ビットコインは信用リスクを伴わない現物資産であり、負債の裏付けではありません。トークン化社会では、多くの資産がスマートコントラクトで管理され可視化されますが、ビットコインほどシンプルで強固な価値保存手段は他にありません。デジタル世界の準備通貨的な地位を得る可能性も指摘されています。実際、2025年時点でビットコインの時価総額は一時サウジアラムコ社の時価総額を抜き、世界資産トップ5入りに迫るほどになりました。これは単なる投機ではなく、長期的な価値保蔵先として資金が流入している証拠です。
長期の視点で見れば、ビットコインの価格上昇余地はまだあるとも言われます。ARKインベストのキャシー・ウッド氏は「2030年までにビットコインが100万ドル(約1億円)を超える可能性がある」と予測しています。強気シナリオでは150万ドルという数字も出ています。これはもちろん前提条件次第の話ですが、仮に10年後ビットコインが今の10倍以上の価格になっていても驚きではないでしょう。供給増やせず需要だけ増えていけば、経済の拡大に応じて1BTCあたりの法定通貨建て価格は膨れざるを得ないからです。
IBITのようなETFを通じた需要だけでも、今後各国で同様の商品が承認されれば、数千億ドル単位の新規マネーがビットコインに向かう可能性があります。また、次の半減期(2024年)以降マイニング供給はさらに減少しますので、需給は締まりやすくなります。デジタルゴールドとしてビットコインを長期保有(HODL)することの価値は、むしろブラックロックの参入で確固たるものになったと言えるでしょう。かつてビットコインが怪しい存在だった頃からコツコツ買い集めてきた人々は、今やその判断が正しかったと胸を張れる状況です。
個人の豊かな未来のために:ビットコイン保有戦略
以上を踏まえ、私たち個人はビットコインとどう向き合うべきでしょうか。「どの程度のBTC保有が理想か?」という問いに明確な答えはありませんが、いくつか参考になる考え方があります。
まず、有名な言葉に「0.28 BTC持てば将来1%の富裕層になれる」というものがあります。これはビットコインの総供給2100万BTCを世界人口で割ると一人当たり0.0027BTCしか行き渡らない計算になり、もしビットコインが世界準備通貨級に普及した場合、0.28BTC保有者は上位1%の富裕層に入るという趣旨です。真偽は状況次第ですが、発想としては興味深いです。また「1BTC持てば平均的な人の400倍の資産を持つことになるかもしれない」という極端な見方もあります。要は、ビットコインは上限が決まっているので一人あたり1BTCですら非常に多いということです。
現実的なアプローチとして、ブラックロックなど伝統機関が示唆するのは「ポートフォリオの数%をビットコインに割り当てる」という戦略です。例えばブラックロック傘下のモデルポートフォリオではビットコインを12%組み入れる動きが見られたと報道されています(実際、2024年にブラックロックはいくつかのマルチアセットファンドにIBITを約1%組み入れました。また、BloombergのETFアナリストは「大多数の投資家にとってビットコインETFへの適切配分は15%程度だろう」と述べています。このくらいであれば全体リスクを大きく損なわずリターン向上が期待できるという判断です。
では具体的な数字で将来価値を考えてみましょう。仮に2030年にビットコインが100万ドル(≒1億2千万円)になるとします。今1BTC=約400万円(※執筆時点)ですから、0.1BTC(40万円相当)でもその時には約1200万円になり、十分な資産と言えます。0.5BTC(200万円相当)なら6000万円、1BTCなら1.2億円です。もちろんこれは楽観シナリオですが、逆に言えば少額でも持っておくと将来大きな差になる可能性があります。たとえ100万ドルまではいかずとも、ビットコインが現在の金の時価総額に並ぶだけで1BTCあたり数十万ドルにはなります(現状ゴールド約9兆ドル、市場の他要因考慮しない単純計算でビットコイン1枚=約50万ドル。
一方、「生活防衛資金はしっかり法定通貨や現金性資産で確保し、余裕資金でビットコインを買う」ことも大切です。ビットコインは長期的には上昇期待でも、短期変動は激しいです。急落局面でも狼狽せず持ち続けるには、なくなっても生活に困らない範囲で投資するのが鉄則です。5%でも自分にとって額が大きすぎるなら1%でも構いません。重要なのはゼロにしないことです。全く持っていないと、万一ビットコイン主導の金融革命が起きた際に恩恵を受けられません。また少額でも持っていれば相場やニュースに自然と関心が向き、知識が深まります。
安全面では、ETFなど間接保有も良い選択肢です。技術に自信がなければIBITのような商品を通じて投資することで盗難リスク等を回避できます(もっとも現時点で日本では現物ビットコインETFは未承認なので、海外ETFを買うか、国内では現物か先物ETFを活用する形になります)。自分で購入する場合は、信頼できる取引所を使い、二段階認証などセキュリティを徹底しましょう。可能ならオフラインのハードウェアウォレットで自己保管することが望ましいですが、それにはリテラシーが必要です。初心者はまず少額を取引所に預けて慣れ、徐々に自己保管に移行するステップでも良いでしょう。
最後に、長期の視野を持つことです。ブラックロックの動きを見てもわかる通り、巨人たちは腰を据えてビットコインやトークン化の未来を作ろうとしています。我々個人も、短期的な値動きに一喜一憂するのではなく、この潮流に長期的に乗る心構えが必要でしょう。ビットコインはしばしば4年サイクルでアップダウンを繰り返しますが、その谷を耐え山を待つ忍耐が報われる可能性は高まっています。何より、ブラックロックという後ろ盾を得たことでビットコインの生存確率は飛躍的に上昇しました。もはや主要国政府が禁止するといったシナリオも現実味が薄いでしょう。そういう意味で、以前より安心して長期投資できる環境になったとも言えます。
おわりに:新しい時代への第一歩
ブラックロックとビットコインの物語は、金融の過去と未来が交錯する壮大なドラマです。リスク管理の鬼才が生んだAladdin、革命児ビットコイン、それらが出会い生まれたIBITとBUIDL——すべては金融構造を作り変えるピースとなっています。中央集権と分散化のせめぎ合いは続きますが、いずれにせよ金融のデジタルシフトは止められません。
私たち個人にできることは、この変化を学び、備え、そして活用することです。幸いビットコインという誰でも買える資産が、その入口として存在します。もし本記事を読んでビットコインに興味を持たれたなら、ぜひ小さな一歩を踏み出してみてください。信頼できる国内取引所で口座を開き、数千円でもビットコインを買ってみる。それだけでも未来の金融に参加する感覚が得られるでしょう。あるいは証券会社で暗号資産関連のETFや投資信託を探してみるのも一つです。
重要なのは行動することです。ブラックロックの動きを「巨人の陰謀だ」と傍観するだけでは何も変わりません。私たちも微力ながらこの新しい金融パズルの一部になり、豊かな未来を自らの手で築いていきましょう。ビットコインを一握り、未来への切符として。そして長い旅路の先に、これまでにない豊かさと自由を手に入れることを願って止みません。
では、今日からできることを始めましょう。「1 SATS」(0.00000001 BTC)から未来は動き出す。 お読みいただきありがとうございました。